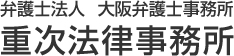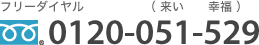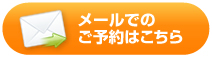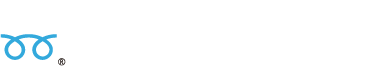同時廃止事件とは(+異時廃止とは)
事業主以外の個人の破産手続きにおいては,管財人が付かない同時廃止事件(同廃事件⇔管財事件)が一般的です。破産事件全体の中でも,同時廃止事件は過半を占め,平成15年では9割を超えていました。近時,その比率は減少傾向にありますが,平成20年以降でも約7割(平成23年速報値で67.5%)が同廃事件となっています。
同時廃止事件(同廃事件)とは,破産手続開始の決定と同時に,破産手続廃止の決定をする事件をいいます(破産法216条1項)。破産法31条だけを見ると,破産手続開始の決定と同時に,破産管財人を選任することになりますが,216条1項により,実際には破産事件の約7割を占める同廃事件では破産管財人が選任されません。
条文上の要件は,「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」であり,管財人を付けるだけの財産がない場合,ということになります。
実際には,下記のような理由によっても,同廃事件か管財事件か,が決められることもあります。
・自己破産の申立人である破産者が,自由財産拡張申立ての必要から,管財報酬を含む予納金(大阪では20万5千円)を納めて,同時廃止でも対応できる案件を,敢えて管財事件にする(現金での自由財産を20万円余減らしても,他の自由財産を拡張したい場合)
・免責決定の判断のために破産管財人を付して調査する必要がある場合,同時廃止事件では免責決定が得られないため,予納金を納めてでも管財事件へ移行させて管財事件とする
同時廃止と似た用語で,異時廃止があります。これは,破産管財人は選任されたが,配当手続費用を支弁するほどの破産財団が形成できないことが,開始決定後に判明した場合に,手続廃止の決定がなされるものです(破産法217条1項)。